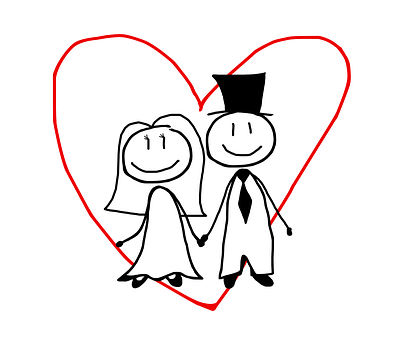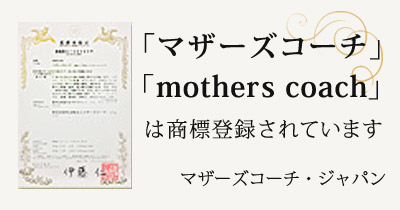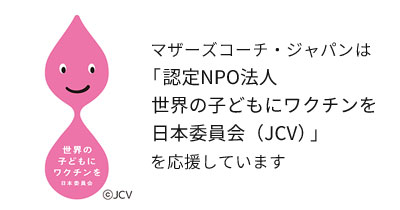こんにちは
「強みで自立する子どもの育成と
母親のイキイキした人生をクリエイト」する
マザーズコーチジャパン代表理事の佐々木のり子です。
本日は、
=======================
「娘の反抗的な態度に疲れました。」
=======================
イヤイヤ期の子育てのコツについてお届けしますね。
お悩みケーススタディ1
働きながら1歳半の娘を育てていますが、イヤイヤ期が
早く来てしまい、イラつく毎日です。
雨の中抱っこひもで歩いている時なんて「歩く!歩く!」
と両足をばたつかせて泣き叫ぶので、抱っこひもから
おろして歩かせようとすると、一歩も歩かず、「抱っこ!抱っこ!」
と泣き叫ぶことの繰り返し。
抱っこひもから降ろした時、娘が地面にへたり込みました。
こういう時に限って雨具を着せていない。
びちゃびちゃになるって分かっているけど、
雨に打たれても泣き止まない娘をボーっと見つめ、
「あー、このまま放置すれば虐待なんだろうな」という
思いが頭をよぎったこともあります。
たぶん雨の中で座っていたのはほんの数秒だっただろうに、
自分がものすごく悪いことをしたような罪悪感に。
子どもが生まれる前、よく「母親は子どもの泣き声だけで
おっぱいがほしいのか、オムツを変えてほしいのか分かる」
と聞いて「へえ」と感心していただけに、娘が求めているものがわからない
自分は母性がないのでは?と思い、子育てに自信がありません。
青空をぼーっと眺めていたら、ふとこのままベランダから飛び降りたら
楽になれるかも、なんて思いがよぎる自分が怖いです。
解決のコツ3
====================
1.自分をケアし、心を満たしてあげましょう
2.自分を客観的に見る視点を持ちましょう
3.子どもの心を勇気づける「存在承認」をしましょう
====================
1.自分をケアし、心を満たしてあげましょう
車がガソリンがないと走らないように、
人もエネルギーが枯渇していては、人の世話はできません。
まずは自分自身のエネルギーを増やしましょう。
あなたががほっとしたり、楽しいと感じられることは何ですか?
例えば、
「せっかく買った新しいコーヒーマシンを使っていない」
「たまには子どもを預けて、美容院できれいにしてもらう」
5分でも自分だけのための時間が取れるようになると
心に余裕が生まれてきます。
余裕がないと思考もネガティブになりがち。
まずは自分を大事にしてあげましょう。
2.自分を客観的に見る視点を持ちましょう
このケースのママさんのように、仕事と家事&育児を
両立し頑張っているワーママさん達も多くなりました。
仕事をしていると同年代の子どものいるママたちと
接する機会が少ないこともあるので、「自分だけ?」
と思う視点があるかもしれませんが、実は世の中のママたち
皆この時期、全員戸惑っています。
自分だけじゃないというのがわかることで状況は変わらなくても
捉え方が客観視できるようになり子育てが少し楽になるかもしれません。
同じ年代の子どもを持つママや先輩ママと接する時間も作ってみましょう。
3.子どもの心を勇気づける「存在承認」をしましょう
ママの心と体が元気になったら、子どもに次のステップを取組んでみましょう。
「子どもの心を勇気づける存在承認」です。これさえやっておけば
子どもの根っこは大丈夫です。すくすく伸びていきますよ。
存在承認とは、何かができたとか、手伝ってくれたとか
その行為に対して承認(認める)のではなく、子どもが存在してくれることこそ
私の喜びなんだと、その人の存在そのものを受け止めることです。
「いつもちゃんと見ていますよ」「受け入れてますよ」と子どもに
伝えたり態度で示すことです。
具体的には、「寝る前にハグをして大好きだよ」伝えたり
「あなたはママの宝物だよ」とお礼を言うなどがあります。
繰り返し子どもの魂にしみこませるようにすると
子どもは生涯あなたに愛されていると感じ、安心して前進することができます。
※この内容は2016年5月にPHP文庫から出版された
佐々木のり子の「ダメ母の私を変えたHAPPY子育てコーチング」
の本から抜粋して子育ての悩みを解決するコツを
ご紹介しています。